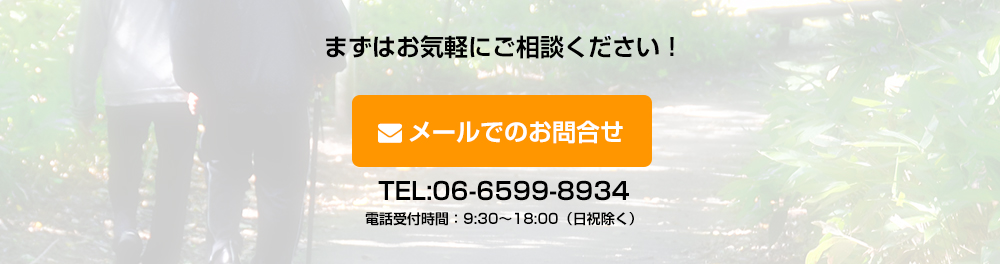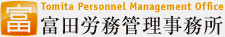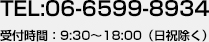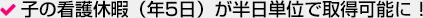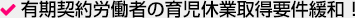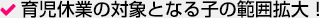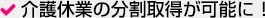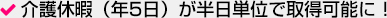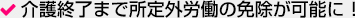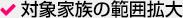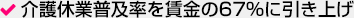従来は1日単位でしか取得できなかった看護休暇が半日単位で取得可能となりました。
従来の取得要件は
- 同じ事業主に継続雇用された期間が1年以上
- 子が1歳以降も雇用継続の見込みがあること
- 子が2歳までの間に更新されないことが明らかでないこと
となっていましたが、改正により
- 同じ事業主に継続雇用された期間が1年以上(変更なし)
- 廃止
- 子が1歳6ヶ月までの間に更新されないことが明らかでないこと
と変更されました。
法律上の親子関係である実子、養子に限られていた範囲が、 法律上の親子関係に準じるといえるような関係(特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子など)にも拡大されました。
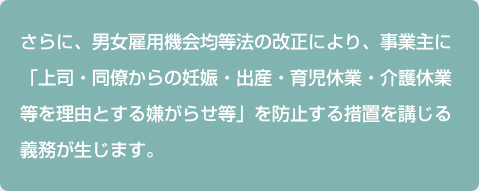
従来は原則1回限りで93日まで取得可能でしたが、改正によって通算93日まで3回を上限に分割取得できるようになりました。選択的措置義務も休業に通算されず別途取得可能で、3年間で少なくとも2回以上利用可能となりました。
従来は1日単位でしか取得できなかった介護休暇が半日単位で取得可能となりました。
従来の取得要件は
- 同じ事業主に継続雇用された期間が1年以上
- 93日が経過する以降も雇用継続の見込みがあること
- 93日が経過した日から1年経過する日までに更新されないことが明らかでないこと
となっていましたが、改正により
- 同じ事業主に継続雇用された期間が1年以上(変更なし)
- 廃止
- 93日が経過した日から6ヶ月経過する日までに更新されないことが明らかでないこと
と変更されました。
同居・扶養していない祖父母・兄弟姉妹・孫も対象となります。
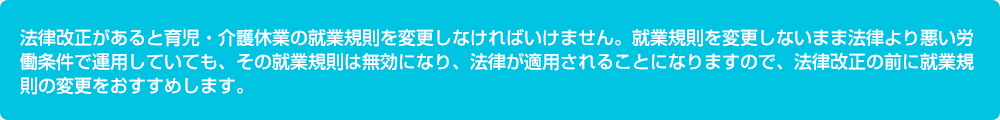
就業規則は経営者と従業員が同じ目標に向かい、それぞれの使命・役割を明確にする「会社のルールブック」です。
就業規則がなかったり、見直しがなされていないと様々なリスクが懸念されます。
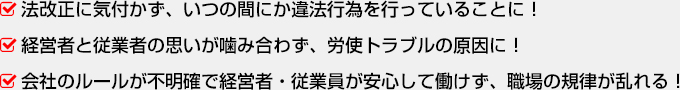
育児・介護休業法は、今回新設された法律や論点、従来から設けられているものを合わせると10項目以上もあります。それぞれの休業、休暇を取得出来る時期や要件、労使協定により対象外とすることができる労働者の範囲なども少しずつ異なっており、制度的に非常に複雑です。お客様の職場の労働環境、就労状況を一つ一つお伺いして育児休業規程、介護休業規程などの作成、改定のお手伝いをいたします。
従業員の育児・介護休業規定を定めると同時に、賃金・退職金規定などについても見直す必要があります。せっかく規程を策定しても、従来の賃金・退職金規定と照らし合わせた際に、従業員にとって不利なものとなってしまうのであれば、従業員は育児・介護休業を積極的に利用できなくなってしまいます。それだけでなく、経営者の思惑外での評価が行われたり、従業員のモチベーション低下を招いたり、会社にとって致命的な結果を招いてしまいます。
育児・介護休業法の改正によって、賃金に関わる規程も見直す必要がでてきます。休業期間中の給与について、経営者・従業員の双方が納得できる給与規定の取り決めをいたします。
育児・介護休業の期間を退職金の支給対象除外期間に算定するかどうかも重要な見直しポイントとなるでしょう。企業にとって退職金の準備負担が少なく、従業員がいきいきと働けるような退職金規定をご提案します。